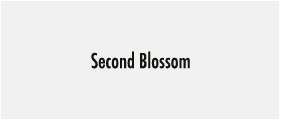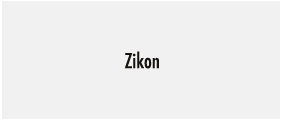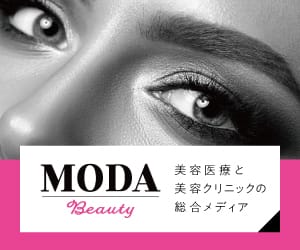ボクシング漫画のみならずすべての漫画における大金字塔といえば『あしたのジョー』! いつの時代も、男も女も、完全燃焼しきった一人の男・ジョーの生き様に焦がれずにはいられません。
原作の梶原一騎氏とちばてつや氏のタッグで生まれた国民的漫画は、1970年代の日本を席巻しました。
今回お話しを伺うのは漫画家ちばてつや氏。
『あしたのジョー』執筆当時のエピソードや作画テクニックなど、ボクたち“心の中の少年”が蘇ってきます。
そのほかにも“ジョーの年齢を超えてしまった大人”も楽しめるお話しが満載。
なかでも「ジョーと紀子ちゃんのデートシーン」は語り継がれる名シーン。
今回、明らかになった、あしたのジョーの核を描くことに至る、ちばてつや氏の葛藤とは?
名作『あしたのジョー』は骨太な作風を得意とする梶原一騎(高森朝雄)先生とのタッグでしたが、ちば先生によるオリジナルキャラクターも見どころのひとつ。
特に「乾物屋の紀子ちゃん」は梶原先生の世界にはいなかった、いわゆる普通の女の子でしたね。
梶原さんのシナリオにもドヤ街の住民は出てきていたんだけど、乾物屋の一家やジョーを慕う子供たちというキャラクターは指定されていなかったね。
紀子がなぜ登場したかというと、私の実家が乾物屋だったんです。
当時の風景をそのまま使ってできたキャラクターだね。
ただしウチは男ばかりの兄弟でしたから、紀子みたいな女の子はいなかったな。

梶原先生の鬼気迫る男の世界とちば先生が表現する人間味、このふたつの塩梅が『あしたのジョー』の魅力を深めたように思います。
少なからず想いあうジョーと紀子ちゃんはデートをします。

このデートシーン。
ボクシング漬けのジョーに、紀子ちゃんが「そんな生き方でいいの?」と疑問を投げつけますが、ちば先生はどんな気持ちでこの問いに対する答えジョーに語らせたのでしょうか?


当時、私はちょうど30歳を少し過ぎたあたりでした。
17歳からずっと漫画を描き続けてきて自問自答していたんだね。
締め切りに追われ、机にしがみつき、病気にもなった。
ジョーを描いていた頃は週刊誌一本に仕事を絞っていたけど、それ以前は少女漫画誌や『週刊ぼくらマガジン』、新聞にも掲載していたと思う。
寝る暇もないくらいとても忙しかったんだ。
『あ~、間もなくワシの命は終わるんだなぁ。これは……長生きできんな』と感じていました。
あの頃はね、右肩上がりの好景気時代で、団塊の世代やそのちょっと下の世代みんなが青春を謳歌していたんです。
ディスコで踊ったり海外旅行に飛んだり、夏はハワイ、冬はスキー。
加山雄三の『若大将シリーズ』じゃないけど、そういう風に若者みんなが遊んでいたわけだ。
それなのに私の青春時代は終わりを迎え、オジさんになりかかっていた。
『青春が、人生が終わってしまう。それでいいのか?!』
と自問自答していました。
だからついデートシーンを描きながら、ジョーに自分自身を重ね合わせたんだろうね。
ジョーはボクシング、私は漫画にどっぷり浸かった日々を送っていたから。
漫画も格闘技みたいなもんなんだよ。
梶原さんと私はボクシングをしていたんだ。
こういうパンチがきたら、「これでどうだ」と全力の拳を返す。
と言っても、作品の上でだよ(笑)。

それぐらいお二人は『あしたのジョー』にエネルギーを込めて作品を練り上げていたんですよね。
血が通ったキャラクターたちが、本当に生き生きと紙面を躍動しています。読んでいると非常に感情移入させられます。
力石徹(主人公ジョーのライバルにして親友)がジョーとの試合直後に死んだときは、読者のみんなが自分の家族や親友が亡くなったかのように葬式をあげてくれました。
全国から多くの人が集まり力石の死を悼んでくれたんです。
そんななか
『まっかに燃えて、最後には灰がまっ白になるような生き方。
自分はそういう風に生きている!
悔いはないじゃないか。
この作品が終わったらパタっと倒れてもいいだろう』
と、私も作品を描きながら感じていたんだろうね。
けれど当時の私は自分がそういうことを感じていたと自覚していなかったんですよ。
ひたすら『ジョーははこんな生き様をして、ある意味可哀そうだ』と思っていた。
子供たちが慕ってくれて楽しそうな瞬間もあったけど……普段は寂しそうで辛そうでしょう。
力石を殺してしまったという気持ちも抱いているから一層ね。


デート中にジョーは生き方について「燃えかすなんかのこりやしない」と完全燃焼への願望を言葉にしたのですが……。
対する紀子ちゃんに「ついていけそうにない」と距離を取られてしまう。
真っ暗闇にジョーがひとり残される一コマが続くのが印象的です。当時の少年誌にしては少し大人のやり取りでしたね。


掲載されたのは『週刊少年マガジン』だったので、読者は小学生から中高生が多かっただろうね。
けれど大学生やサラリーマンも読んでいたから、若者たちに向けて描いているという意識があったよ。
子供に向けてという意識はさほどなかったなぁ。
この何気ないデートシーンですが、ジョーにとって最後の闘いとなるホセ・メンドーサ戦につながる重要なエピソードとなっていきました。
あのラストシーンのイメージはいつ頃から頭に浮かんでいましたか?
いやぁ、あんまり意識はしていなかったと思いますよ。
私は描いたそばからすぐ忘れちゃうし、自分が描いた漫画を読み返さないんだ。
漫画家って誰でもそうだけど、読み返すと描き直したくなっちゃう。
『ここを直したい、あそこも!』とね。
それを実際にやってしまったのが手塚治虫さん。
ですが、たいていの読者は描き直されるとガッカリしちゃうみたいでね。
最初に描いたものがいいようです。
たとえ画が荒れていようと話が乱暴だろうと「最初のままにしておいてほしかった!」と思うみたいなんだ。
そういう声を聞いていたから、私は描き直すことのないように読み返していなかったんです。
ジョーのラストシーンをどうしようか考えているときでさえ、デートのエピソードはすっかり忘れていた。
でも私がすごく悩んでいてね。
吉田さんという編集者が担当だったんですが『あしたのジョー』を全部読み返して「この回を読んでください!」と言ってきたんだ。
それが紀子とのデートシーンです。
しかし私は「いやいや、読み返すことはしませんよ」と拒んだの(笑)。

描き直したくなったら、ますますラストシーン完成が遠のきそうですもんね(笑)。
いつまでたってもラストシーンが決まらないもんだから編集さんもしつこく食い下がり、デートシーンにしおりを挟んだものを僕の仕事部屋に置いていったんだよ。
そうしている内に締め切りが過ぎて、いよいよ私も追い詰められた。
それでとうとう読み返したんだ、あのデートシーンを。
このコマを目にしたときに、ふっとラストシーンが頭に浮かんだ。

計算や伏線なしで、あのデートシーンとラストシーンが繋がっていったんですね。
プロなら計算をするんでしょうけど、私はそういうタイプじゃないんだろうね。
ジョーや段平、力石、紀子、葉子という人間たちの日記をつけているつもりで描いていたから。人間群像だよね。
ジョーを中心とした人間たちの生き様です。
『コイツはどこへ行っちゃうんだろう』と思いながら、描いていたよ。
梶原一騎さんもそうだったと思う。
キャラクターの設定はある程度決まっていたけど、最後がどうなるかは決めていなかった。
そう思うと、たった一回のデートが『あしたのジョー』の大事な核になってくれるとはねえ。
実際、原作のある漫画というのは結末が決まっているものが多いでしょう。
たとえば漫画家の井上雄彦さんが『バガボンド』を描いているね。
剣豪の宮本武蔵の話です。井上さんは原作を読み切った後で『バガボンド』を作り上げているんじゃないかと思うけど、『あしたのジョー』は梶原さんと私の二人、あるいは編集さんを交えて意見を言い合いながら毎回練り上げて作っていた。
梶原さんからシナリオが届いて読んでから、『う~ん、このストーリは読者の子供には向いていないかな、わかりにくいだろう』と変えちゃったりもしました。
それで一時期は梶原さんとモメたこともあったけど、徐々に私の考えをわかってくれたんだ。
梶原さんも『サァ、この話をちばがどう描くか!』という風に、ゲラを見てからその続きを考えてくれたりね。
話がどう進むか、ジョーたちの未来がどうなるかは、かっちりとは決まっていなかったよ。

創作はかなりのエネルギーを要しただろうと想像できます。
『あしたのジョー』連載中は骨身を削り、十二指腸潰瘍になりながらペンを手にしていた時期でもあったと伺っています。
漫画を描き始めて十何年が経ち、ちょうど疲れが出てきたんでしょう。
月刊誌であればゆっくり休む時期があったんだけどね。
編集者に原稿を渡せば3~4日はぐたーっと過ごせたの。
でも週刊誌は違った。描き終えて渡しても、すぐに次の締め切りが迫る。
自分のペースがわからなくて体調を崩してしまったんだ。
だけどそのことがあって、ジョーがまっ白に燃え尽きていく生き様に重なっていったように思うよ。
ちば先生自らの悩みや体の変化なども作品の一部みたいに思えてきました。
『あしたのジョー』はちば先生のほかの作品と比べてタッチが異なるような……。
陰影、闘いによる傷といった細部の描き込みが凄い!
梶原さんが作る話はやや文学的なところがありましたからね。
私が知らなかった大人の世界、裏社会で生きる怪しげな人間もたくさん出てきました。
そういう雰囲気を出そうとすると、だんだん絵がリアルになっていくんです。
作品初期のジョーは中学三年生くらいの男の子。
それが、減量問題だ人の生き死にだとかを描いていくうちに……。

ふっくらとした頬がこけていきましたもんね。
表情もどこかフッと寂寥感が滲んでいて、大人の男の顔に。
仕草や表情、背景など、線が増えていくにつれて仕事が大変になったのでは?
私ひとりで仕事をしているわけじゃなく、スタッフがいてくれましたから。
私の下描きや写真を見せたりして、描いてもらっていました。
すると私の描き込みや梶原さんの世界観に合わせてくれるようになるんだね。
そうして『あしたのジョー』は少しづつ劇画調のタッチになっていったんだ。
難敵・金竜飛との闘いの書き込みも凄まじかったです。
ペン画の世界だねえ。

瞬間を切り取る描写のテクニックも、ちば先生独特のリズムがあります。
たとえばボクシングシーン。力石渾身のパンチがジョーに炸裂する……かしないかの一瞬を見開き最後の一コマに描き、読者に次のページをめくらせる。
このリズムに引き込まれるんです!
話の展開だけを考えれば、見開きの最後で力石に殴られたジョーは、ページをめくったところですぐに倒れていても構わないんだよね。
だけどパンチの衝撃や観客の顔みたいなものを入れていきたい。
描きながら『読者はこの躍動感をわかってくれるかな。動きを捉えてくれるかな』と考えるんです。
そこで一旦描いたものを伏せて、読み直してみる。
すると『ここにはひとつ、間をおいた方がいい』と改めて感じることがあるんだ。
実際に間を入れたら画が生き生きとしてきたり、あるいは衝撃がより見る方へ迫ってくる……。
締め切りまでにこうやって、描いては消し、描いては読み直し『もっと迫力がほしいなあ』と思いながら再び描き直す。
これが私の癖なんでしょうね。
スルスル~っと描けるものではないんだよ。
一コマ足してみたり、めくりを活用したりしないと。

ストーリーを追わせるだけでなく、その時に何が起きているか、空気感はどんなものか、熱量、音や光、匂い……。そういった描写が随所にみられますね。
若い頃からそうだったんだけど、コマを足すんだね。
そんなだから編集者に「物語の流れからすればこのコマは要らないでしょう」とよく言われたんだ。
「話に関係ないコマは削ってストーリーを早く進めてくれ」と。
テンポの速い手塚治虫さんや石ノ森章太郎さんの担当をしていた人が編集長になったときに、特に言われたね。
けれど私にとっては大事なコマなので、削るなんてできない。
だから話し合いをしたところ「この一つひとつのコマは、ちばさん独特のペースなんだね」とわかってもらえたんです。
「それがちばさんらしさなんだから」と大事にしてもらえるようになったんだ。
最初はページ数を水増ししていると思われていたからね。
ある少女漫画を描いていたころ、私はそこに登場する一家の長閑さを描きたくなった。その家族は団地に住んでいる。
豆腐屋さんがやってきて、子どもが買いに行くんだ。
玄関を出て階段を降り始めるんだけど「1、2、3……」と一段一段を数えだす。
こういうのも私の無意識の癖なんです。
階段を踏むリズム、傘を欄干に当てながら道を歩くというような、ちょっとした動きだね。
最後の階段を降りて、子供は豆腐屋さんに辿り着き「お豆腐ちょうだい!」と言う。
ここまでに2、3ページを使ったら「水増しだろう!」と怒られました(笑)。

でも、そういった一コマ一コマが大事なんですよね!
うん、水増しじゃないんだよ。
それに楽しんで描いているんだろうね、私は。
お豆腐屋さんだってそうだよ。
このお豆腐屋さんは「ちょっと待って。ハイひとつ!」と油揚げを半分にちぎって子どもの口に入れてやり、自分も食べる人だなんて頭に浮かぶんだ。
そして描いちゃう。
育った下町で見てきた朝の情景なんだろうなぁ。
どうも私はね、ものを食べたりお話しをするのに時間をかけすぎなの。
現実のわが家での朝食も、一番最初に私が食べ始めているのに、子どもたちが「ごちそうさまー!」と学校に出て行ったあともひとりで黙々と食べ続けている(笑)。
一生懸命急いでいるんだけど、自分のペースというか一つの流れがあって、自然に時間がかかるんだ。
そのペースを壊してしまうと、体調が悪くなる。
私の中ではそうやって時間がゆっくり回っているんだよ。

『あしたのジョー』がこれほどまでに愛される理由は、梶原先生による素晴らしい原作と、ちばてつや先生が掬いあげ描ききった登場人物たちの生き様が、ボクらの心を強烈に打ったから。
忙しい現代社会、効率性を追いがちで「悔いのないくらい燃え上がった!」という手応えを感じる機会は少なくなったかもしれません。
ですがちば先生のように、自分のペースで情熱の火を灯し続けてみませんか?
次回インタビューでは、原作者の梶原一騎先生を偲ぶエピソードやクリエイティブな人間が持つ創作の苦しみなどをお聞きします。
写真:田形千紘 文:鈴木舞
編集・構成 MOC(モック)編集部
人生100年時代を楽しむ、
大人の生き方マガジンMOC(モック)
Moment Of Choice-MOC.STYLE