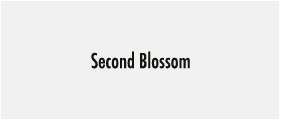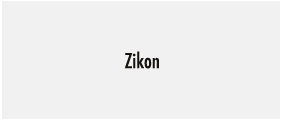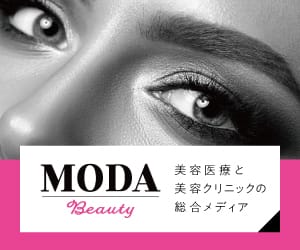AI(人工知能)という言葉を最近よく耳にします。
しかし実際のところ、AIがどんなものでどんな影響を私たちに与えるのか、これからAIはどう進化していくのか、気になることは山ほどあります。
人生100年時代を生きる私たちの生活を、AIはどう変えるのでしょうか?
IT・データ解析サービスを展開する株式会社LIFAAの代表取締役、平井太郎氏に話を伺いました。
「昔からあったものが急に最近取り沙汰されている印象がある」
近年、「AI」という言葉をよく耳にします。
生活のあらゆる場面でAIが導入されていますよね。
平井さんとしてはどういう眼差しでこの事象を見ているのでしょうか?
そもそもAIの研究は自分が大学生の時からありました。
なので、もう20年前ぐらいからあるんですよ。
でも実は呼び方が変わっていて、今は「ディープラーニング」や「機械学習」という言葉になっているじゃないですか。
機械学習は昔でいう「教師あり学習」。答え合わせをしてあげて、だんだん育てていく。
ディープラーニングは「教師なし学習」と昔は呼ばれていて、大量のインプットデータによって、どうなるのか出題者も分からないけれど、環境によってうまく動くようになっていくものなんですね。
昔からあったものが急に最近取り沙汰されている印象があります。
では、最先端の研究をされていた方にとってはそれほど騒ぐことではない、と。
はい、新しくはないですよ。
これまで研究していたのを、Amazonやマイクロソフト、Googleなどがプログラムを簡単にいろんな人が使えるようにしたことが大きいかなと思います。
論文を見てプログラミングできる人間はほとんどいないし、科学者は論文を理解できるけどプログラムを作れるわけじゃない。
それを大企業がやってくれたわけです。
AIというのは進化していく。私たちの生活面ではどんな変化があるのでしょうか?
例えば、簡単な質疑応答はもう全部AIが答えられます。
今まで人力がやってきたQ&AをAIが回答する仕組みが実際にあります。
単純なコミュニケーションはAIに乗っ取られていく…。
そうですね。
取って代わられるという感じでしょうか。
だからコールセンターなどは、最終的にはAIだけでやるんじゃないかなという気がします。
コールセンターをAIが代用していくとなると、どんどん人の働き方も変わってくると想像するのですが、人間の価値ある働き方はどういう風になるのでしょう?
例えば、AIは手先指先を使う細かい作業が苦手です。
その辺は、まだAIが代用できるのはまだ遠い未来の話かなと思います。
工場でいろいろ織物をAIができる日はしばらくは来ないんじゃないかな。

家事全般をAIがやってくれる時代へ
生活の空間の中でAIが入ってくると、どのようなメリットがあるのでしょう?
例えば、検索エンジン。
自分が学生の頃は、インターネットがまだそこまで発達していなかったし、googleもなかったけれど、今は当たり前のように使っている。
でも、人によってはこんな簡単な検索方法も知らないし、知らない人にとっては難しい技術じゃないですか。
僕は、最終的にAIが教師になれるぐらいの技術を持つと思う。
そうすると、例えばITを全然知らないおじいちゃん、おばあちゃんにAIがITの使い方を教えることができるんですよ。
あとは、そうですね、一般家庭で執事を雇うことは普通、無理じゃないですか。
でも、AIであれば複製がいくらでも可能なので、AIが執事の役割をしてくれて、生活が快適になることは考えられます。
最終的に家事をやってくれるんですか?
そうですね。
あとはテレビの予約や植物の水やりなど日常的なこともやってくれるようになるんじゃないですかね。
お手伝いさんを簡単に雇えるような世界が来たらいいなと思います。
ロボット掃除機のルンバはAIですか?
はい、完全にAIですね。
昔、ルンバが発売された頃に、拭き掃除あればなと思っていたけれど、床の拭き掃除ができるようになりましたから。
時代は進んでいますね。
家事をAIが担うようになると、生活の上で時間ができるので、いろんな他のことに余裕を持ってやれるんじゃないかと思います。
生活空間をクリエイティブに、スマートにするのにもAIは役立ちそうですよね。
例えば、家に帰ってきたら、部屋の明かりがつく。
今の技術はセンサーでやっているけれど、それをAIは例えば音がしたら明かりをつけるとかね。
僕、ペットとして猫を飼っているんですけど、僕が家に近づいているだけで、猫が玄関先まで来てくれているんです。
猫という単純な思考理論でもそれぐらいはやるので、AIだったらもっと有効的にやるかもしれない(笑)
AIは猫を超えられるか?
AIは猫を超えられるのでしょうか?
全然超えられると思いますね。
AIの中で「記号着地」という問題があります。
人間はすごく不思議なんですよ。
例えば、花について、一生に一度も見たことない花でも「花」だと分かりますよね。
その時に理論上どうやっているか判別しているか分からないんですよ。
一方、うちの猫は2匹いるんですけど、1匹が手術に出て、包帯をぐるぐる巻いて帰ってきたんですよ。
そしたら残っていた猫が「知らん猫だ!」と思ったみたいで(笑)。
認識できないみたいです。慣れるのに3日ぐらいかかりましたね。
猫の記号認証よりも精度が高い記号認証をAIができる、と。
今、顔認証の技術がありますよね。
iPhonXだとフェイス認証でロック解除できるじゃないですか。
あの辺まで技術は行っているんですよ。
そもそもあれはAIを使って分析をかけている。
AIのディープラーニングというもので、顔写真を何億枚と全部データで入力して、出てきた特徴の分類でやっているはずなんです。
AIは即時的なものだけではなくて、より便利にするためのデータ解析にもよく使われているんです。使い方は無限大です。
AIは「これから」の技術ではなく、「いままでも、これからも」の技術であるそうです。
ではAIは、私たち人間と未来を一緒に築いていく「パートナー」か、それとも、私たちを超越していく「未知の存在」になり得るのか――。
気になる続きは第2回インタビューでご紹介します。

写真:田形千紘 文:五月女菜穂
編集・構成 MOC(モック)編集部
人生100年時代を楽しむ、
大人の生き方マガジンMOC(モック)
Moment Of Choice-MOC.STYLE