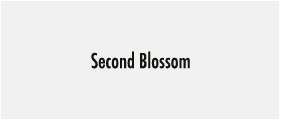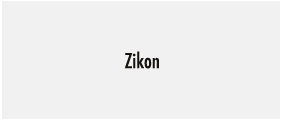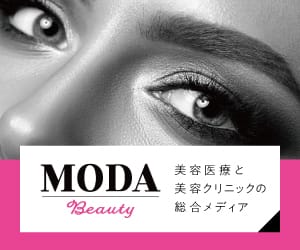古代日本はどこで生まれたのか。
どのようにして島国の地方に大和朝廷の影響力が及んでいったのか、謎の一族・阿波忌部氏の働きとはなんだったのか――。
こういった日本の歴史にまつわるミステリーは尽きることなく、私たちの好奇心を刺激します。
MOCでは阿波忌部氏研究に力を注ぐ林博章氏に、歴史の謎のヒントを聞いてきました。
時代は令和元年。
大嘗祭に向けて、日本の成り立ちや古代国家の発展についてみなさんも一緒に考えてみましょう!
林先生は、邪馬台国を考えるうえで阿波忌部氏が重要な働きをしたと考えていますね。
徳島で生まれた技術などを各地に供給していった阿波忌部氏。
忌部氏の動きを追うことで、日本の成り立ちが見えてきそうな気がします。
古代日本国家のシステムの一部の成り立ちには、忌部氏が重要な役割を果たしてきました。
今年は「日本の始まりはどこにあるのか」いう謎に注目が集まりつつあります。
不思議なことに去年と今年にかけて注目度が上昇しています。
まるで大嘗祭の始まりを待っていたかのように。

忌部氏の足跡は全国に散っているのですよね?
痕跡は全国にたくさん残っています。
遺跡の中をきちんと見ると、ヒントが見えてくるんですよ。
日本海側からいくと島根県の隠岐の島。
現代でも国土防衛の位置に当たる場所ですね。
隠岐の島にある『水若酢神社』では、代々の宮司しか忌部を名乗れません。
忌部氏は古代日本の成り立ちを感じさせます。
忌部氏の足跡を感じる土地を、林氏にピックアップしていただきました。
西日本
島根県
・『忌部神社』は松江市東忌部町にある。松江市玉造町の『玉作湯神社』は、勾玉と関係があり、出雲忌部が居た。
・『大麻山神社』は、島根県西部、石見国が昔あったとされる地方で、現在は浜田市三隅町にあり、忌部氏が麻を植えという伝承が残る。
和歌山県
・紀伊神社の本拠地、和歌山市鳴神に『鳴(なる)神社』がある。
・「井辺」という地名もあり、読み方は「いんべ」。
岡山県
・備前焼を伝統工芸とする備前市に「伊部」という地名があり、「いんべ」と読む。陶祖として『忌部神社』が祀られる。
讃岐地方
・三豊市豊中町に讃岐忌部の本拠地となる『忌部神社』がある。
東日本
栃木県
・小山市粟宮に『安房神社』がある。阿波から出発して栃木に辿り着いた忌部の祖先を祀った神社。食物の粟を神輿に載せる日本唯一の粟柄祭が存在する。
千葉県
・房総半島の館山市布良の『布良崎(めらさき)神社』は阿波忌部が上陸した神社である。
館山市大神宮には『安房神社』がある。
・勝浦市の『遠見岬(とみさき)神社』。阿波から出発した子孫が宮司家となっている。
西から東へと阿波忌部氏の足跡は長距離に渡っています。
島根県以西には忌部の足跡は見つかっていますか?
九州における忌部の痕跡は今のところ確かめていません。

なるほど。
鉄技術は九州から来たとされますから、九州と忌部氏との関わりのミステリーも気になっちゃいますね。
ところで「忌部」というのは名字のように名乗れるものでしょうか?
現代の名字にあたる前に、忌部をつけます。
たとえば岡島さんなら「忌部岡島」です。
明治時代に入ってからは忌部がつかなくなりました。
現代の子孫の中には、自分が忌部氏の末裔だと知らない人もいそうです。
忌部氏かどうかはどのように調べますか?
明治以前の系図か伝承、巻き物などを調べてみてはいかがでしょう。
なるほど、自分の家の家系図をまずは探してみようかな。
全国に散っていった忌部氏は、各地に技術や社会制度の根をおろしました。
ですがなぜ忌部氏はあの時代に苦労をして地方に散らばっていく必要があったのでしょう?
この謎はまだ明らかになっていません。
考えられるのは気候変動です。
当時のデータを分析すると、洪水で水位が上昇していたことがわかります。
それは2世紀末の「倭国大乱」という時期で、国中が荒れていました。
水位が上昇して収穫に影響が出て、米を十分に食べられなくなったようです。
さらに鉄器の普及もありました。
鉄器によって生産力があがると、人口が増えます。
おそらく忌部族だけが移動したのではなく、他の数多くの民族が移動していったのではないでしょうか。


洪水や人口増加によって、それまでの社会を保てなくなったために地方へ進出したということですか?
そうですね。
忌部族の動きを見ると、戦争をせずに地域をまとめるのがうまいという特徴があります。
争いがないというと嘘になるかもしれませんが、地域の風土に応じてそこに必要な技術を提供し、ある程度平和的に地方へ定着していったように思います。
──忌部氏の地方進出によって、日本という国家の礎が広い地域で成立していったというのはとても興味深いです。
令和という新しい時代に今一度古代日本について考えた時、忌部氏からのメッセージをどのように受け取ることができるでしょう?
平和、共存でしょうか。
徳島の山に存在していた忌部氏の集落では、現在も「give and give」の精神、お接待の精神が生き続けています。
「どうぞ、どうぞ、持っていき」の世界です。
そういう精神を忌部氏は持っていたように感じますし、関東の伝承にもさまざまなかたちで残されています。

そして迎える大嘗祭。
林先生は大嘗祭直前に講演会を行いますので、より深いお話を聞けることを楽しみにしています。
東京に麁服が運ばれる少し前に、関東の人にもっと日本について知っていただきたいですね。
大事なのは10月に勉強していただいて、11月の大嘗祭に十分注目していただくことです。
11月9日(土)に東京の北区王子の北とぴあで講演会を行います。
「日本の原点とは何か」を見つめて、私たちが暮らす日本について考えてもらいたいと思います。
また、日本の原点を見詰め未来を創る研究所である『一般社団法人 忌部文化研究所』を心ある皆様に支援していただければと思っています。
大嘗祭まであと少し。
古代日本から続く王権承継の伝統儀式には、日本各地からの想いが集まります。
歴史的瞬間に立ち会う前に日本の成り立ちを学び直すことで、世の中がより色鮮やかに豊かに見えてきそうです。
忌部氏から令和へと、平和と共存の精神をつなげていきましょう。

写真:塩川雄也 文:MOC編集部
編集・構成 MOC(モック)編集部
人生100年時代を楽しむ、
大人の生き方マガジンMOC(モック)
Moment Of Choice-MOC.STYLE