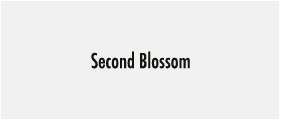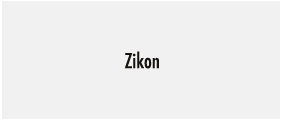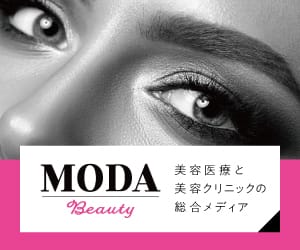心と体のマネジメントにますます注目が集まる人生100年時代のストレス社会。
皮膚と脳との関係性を研究する山口創先生に、触れあいがもたらす癒しの効果について教えていただきます。
インタビュー第ニ弾の今回は、肌と肌とのタッチが繋ぐ親子関係などについて話を伺いました。
触れ合う前の人間関係の築きが大切なんですね。
〝触れよう”としたときに、それが人のためなのか、自分のためなのかでも、効果は大きく変わりますか?
人のために触れようとすると、自然に触れ方がゆっくりになるんです。
赤ちゃんに触れるときもだし、恋人に触れるときもです。
自然とゆっくりになる。そうすると、触れられた側は心地よく感じるんです。
一方、自分本位に触れるときはそういう触れ方ではないんです。
触れた側と触れられた側の間に、〝体の同調”が起こらない。
手を一方的に速く動かす傾向があります。
相手のために触れると相手と自分の体が同調して、呼吸のリズムや心拍数が似てくるんですね。
たとえば転んだ子どもに対して、親が「痛いの痛いの飛んでいけ~」と触ってあげる。
すると痛みが和らぎます。
自分本位の触れ方をしてしまうと同調は起こりません。

触れかたひとつで気持ちの繋がりの深さが違う?
そういうことですね。
相手のことを思いながら触れるとオキシトシンが両方(触る側/触られる側)が分泌されるので絆が深まりますし、お互いに健康にもなれます。
この触れかたの〝質”に、最近私は興味を持っているんですよ。
たとえばですね、子どもに触れるという場面。
従来であれば愛情を持って触れるのが大事だと思っていました。
それはそれで大事だと思うんですけど、必ずしもそうとは限らないんです。
親からしても、いつでも純粋な愛情だけで子どもに触れていられるかというと……。
そうではないですよね。
愛情にプラスして親のエゴのような部分がくっついていて、そういったものが無意識のうちに触れ方に現れてしまうのです。
すると子どもはどう感じるでしょう。
愛情よりも「イイ子にしてほしいんだな」というようなことを感じます。
タッチにくっついてきた親の気持ちを察するんです。
それが嫌になったり重荷になったりすることがありますね。
身に覚えがあります……!
そういったことを避けるためには、〝思いを持たずにただ触れる”という試みが必要なのではないでしょうか。
こんな実験があります。
触る人と触られる人を用意します。
触る人は、なんにも思いを持たずにただ触れるんです。
すると、触れられた側はどう感じるでしょう。
面白いことに、触られた側は自分が欲しいメッセージを感じ取る、ということがわかりました。
触る側が何も考えていないからこそ、触られる側はその効果を自由に創造できる余地があるんですね。
自分は誰からも認められていない、孤独なんだと思っている人の実験結果はどんなだったか。
思いを持たないタッチをされることで、「自分は認められた」というメッセージとして感じました。
褒められたいけど誰も褒めてくれない、と思っている人は、無心のタッチを通して「褒められた」というメッセージが自分のなかに生まれたんです。
その人それぞれが抱いている心の空白といいますか、欲しがっているけど得ることができない部分ってありますよね。
そこを埋めるメッセージを自由に作り出し、それによって心のバランスをとろうとする。
そんな自発的な変化を、思いを持たないタッチがもたらしてくれるということがわかってきました。

悩める中高年にはどのような〝タッチ”が向いているのでしょう。
中高年世代ですとお子さんがいる場合、子どもは思春期だったりしますね。
夫婦間のタッチと、親子間のタッチという2つの視点を考えましょう。
お子さんが思春期の年齢になっても、夫婦でタッチをしている方はけっこういらっしゃいますよ。
そして子どももさほど親のタッチに抵抗を感じていないんです。
子どもが小さい時から夫婦でタッチをしていると、子どもはその風景に慣れますから。
幼い頃からのタッチの経験というのは、年齢を重ねてからも影響はありますね。
小さい頃から人と触れあっていると、タッチに照れてしまうという感覚にはなりづらいんです。
ただ、思春期に親とべったりするのを嫌がるのは当然と言えば当然のことです。
それでは思春期の子どもとどう触れ合えばいいかというと、やはり触れ方を変えてあげる必要はあります。
今までと同じようにベタっと触れるのではなく、部活終わりに子どもが疲れていたら肩をもんであげると子どもは喜びますよ。
子ども扱いしたタッチではなく、大人扱いをしたタッチですね。
そうですね。
「勉強、頑張れよ!」と背中を叩くこともいいですね。
そういうタッチであれば抵抗なくできると思いますし、子どももまた受け入れられる。
毎日そういうタッチを続けていれば、抵抗はなくなっていくかなと思います。
日本人ってある年齢になると、親子でまったく触れあわなくなるのが特徴なんです。
でもたとえばインドの親子は違います。
お母さんは息子が大人になっても脂をつけて頭皮のマッサージしているそうなんです。
だからでしょうか。
親子の関係がずっと良好なんです。
たしかに触れたり触られたりすると、親近感が湧きます。
タッチが減少すると、人間関係はどんどん疎遠になるのでしょうか。
バリア機能といいますか、壁が出来てしまいますね。
会話によって壁を取り払うことはできますが、スキンシップをすることで一気に壁はなくなります。
ですからスキンシップをうまく使うと、すごく有効だと思います。
握手もすごくいいですね。
アメリカではビジネスシーンで握手をするのが普通なんです。
握手をしてから会話をするほうが、より相手のことを信頼できるため商談がまとまりやすいと論じている研究もあります。
日本のビジネスシーンでは、挨拶はお辞儀だけで済ませますから触れあいませんね。
ですからなかなか初対面で仲良くなりにくいんですよ。

人間は身体の60%以上が液体であるから、流体としての自分を意識しなさい。
と著書に書いていらしたのが面白かったです。
ダイナミックな考えですね。
観念的で抽象度の高い話ですが……。
〝境界”の感覚という意味ですね。
皮膚が人間の境界の感覚なんです。
心理的にいうと、鎧を身につけたようながっちりとした境界感覚であったり、逆に自分が希薄であるような感覚であったり、境界の感覚の強さは人によって様々です。
そのなかで私が述べた流体としての境界というのは、「人からの影響を受けるし、自分も影響を与えられる。
そんな交流が行われるような境界」という考え方です。
西洋の文化は境界をガチっと固めて、自己と他人とを分けたうえで自己主張や権利行使をします。
日本人はむしろ境界を曖昧にして、相手の一部は自分の中にあるし、自分も相手の中に入り込んでいるというような、お互いに共通の部分を持ちつつ関係を営みます。
そのような人間関係を営んでいることこそが〝日本人の幸福の原点”だと私は思っているんです。
他人のアイデンティティーを自分のアイデンティティーに取り込みつつ、自分のアイデンティティーが他人の中にも入り込む。
そういう境界をつくっていけたら、日本人の幸福度はあがるんじゃないかと考えます。
お互いが混じり合う場所をつくりだす?
そうです。
日本人ならではですね。
混じり合うというと気になるのが、母親と赤ちゃんの関係性です。
赤ちゃんは、自分とお母さんとの境界を感じているのでしょうか。
この世に生まれたからといって、お母さんと自分が別の人だという認識はないですね。
一年ぐらいはそういう状態が続いていて、自分はお母さんの一部であるというか一体化したような感覚を持っているんです。
それは、くすぐってみるとわかるんです。
自分で自分をくすぐってみてください。
くすぐったくないじゃないですか。
人からくすぐられるから、くすぐったいのです。
だからお母さんが赤ちゃんをくすぐったとき、くすぐったがらないのであれば、赤ちゃんは自分で自分をくすぐっているという感覚を持っている。
つまり、母親と自分は同じ人物だと思っている。
逆にくすぐられて笑ったとすると、それは自分とは違う人にくすぐられたんだという認識ができていることになります。
生後7、8か月くらいから赤ちゃんはくすぐられたときに笑うようになるのがわかります。
自分とお母さんは違う人間だという認識ができるのがその頃です。
比喩的に表現すると、赤ちゃんとお母さんは一枚の布でくるまれていて、赤ちゃんはそれを境界に感じている。
自分だけではなくて、お母さんも一緒にくるまれているんです。
成長するにつれてその境界がだんだんしぼんできて……、ここ(自分の体の輪郭)に落ち着いてくるんです。

タッチの仕方によって、赤ちゃんの心や知能、成長の変化は大きいようですね。
最近注目されているのがやはりオキシトシンの効果なんです。
赤ちゃんにとってオキシトシンがなぜ大事かというと、生後1歳くらいまでにオキシトシン細胞の数がかなり決まってしまうからです。
そうすると、一生の間にどのくらいのオキシトシンを作れるかが大体決まってしまいます。
・記憶力を強くする
・ストレスに強くなる
オキシトシンにはこのような代表的な効果があります。
小さいころにたくさん触れてあげると、生涯オキシトシンを出しやすい脳に育つので、記憶力がいい、ストレスに強い脳のまま生きていけるんです。
母親とのスキンシップを追った研究成果が出ています。
生後の早いうちによく触れられていた赤ちゃんほど、遺伝子に変化が見られるという研究です。特に免疫系と代謝系。
生後早いうちの身体接触によって、このふたつのはたらきが決まってくるという論文が発表されました。
小さい頃に触ってもらうと、体の健康にも大きな影響が出てくるんですね。
家庭生活がうまくいっていると、お父さんお母さん同士も触れ合いの機会が多いと思いますが、そこに子どもが影響されることもありますか?
やはりそれはありますね。
夫婦仲があまりよくない家庭では、子どもへのタッチの機会も少なくなりがちです。
まずは夫婦間のスキンシップを増やすというのはいいかもしれませんね。

子ども、特に赤ちゃんへのタッチですが、なかなか戸惑う面もあります。
お父さんよりお母さん、お母さんよりおばあちゃんの抱っこが好き、という赤ちゃんはいますよね。
タッチの上手い下手って、如実に出てしまうんでしょうか。
ありますねぇ(笑)!
子育てをしたおばあちゃんは抱き方がうまいです。
圧力のかけ方、触れ方。
若い人ほど技術がないので、抱き方があまりうまくないことも多いです。
調査してみると、抱き方にも特徴が出ました。
重心が上すぎて肩に赤ちゃんを担ぐように抱いていたり、あるいは低すぎて手だけで抱いていたり。
赤ちゃんからしても気持ちよくないので、そのままだとだっこ嫌いになっちゃう。
触る側が緊張したり不安でいると、それが手や腕など体を通して赤ちゃんに伝わりますね。
ストレスを受けた状態でだっこすると、赤ちゃんはそれに同調してしまいます。
できるだけリラックスしてだっこしましょう。
緊張したりイライラしたりしていると、皮膚の温度が低下してしまうんです。
交感神経が優位になるためです。
その冷たさが赤ちゃんに伝わって、赤ちゃんのストレスになります。
ですが緊張しないように緊張しないようにと、プレッシャーを感じる必要はありませんよ。
だっこはたくさんしてあげてください。
赤ちゃんの頃からだっこは積極的にだっこしたほうがいいんですね。
はい。データをきちんととってあります。
タッチが多いか少ないかで、大人になってからも違いが生まれるんです。
子どもの頃によく触れられたと思っている人ほど、大人になってから触れられることに抵抗がないし、タッチをポジティブに解釈できるんですね。
ポンポンと触れられたとき、「励まされた」「心が落ち着いた」と感じます。
逆にあまりタッチされなかった人は「緊張した」「気持ち悪かった」とネガティブに解釈してしまうようです。
触られることが嫌な時って、もちろんありますよね。
ですが、タッチの経験が多いほど、触られることにある程度は過敏に反応しなくなるとは思います。
誰だって、幸せな人生を送りたい。
その鍵のひとつが幸せホルモン・オキシトシン。
人間の輪郭をかたちどる皮膚は、実は目には見えない「心」の重要な部分に大きな影響力を持っているようです。
次回インタビューでは、触れあいの力を活用して私たちが目指したい社会の在り方とは何か、人生の歩み方とはどんなものか、山口先生の考えを伺います。

写真:田形千紘 文:鈴木舞
編集・構成 MOC(モック)編集部
人生100年時代を楽しむ、
大人の生き方マガジンMOC(モック)
Moment Of Choice-MOC.STYLE